平均寿命・健康寿命の延伸や高齢者の就業意欲の高まりを背景に、働きながら年金を受け取る仕組みをより柔軟にし、人材確保や技能継承につなげるため在職老齢年金制度が見直されます。
1.改正ポイント(2026年4月施行)
年金減額の基準額(賃金と老齢厚生年金を合わせた額)が月51万円から月62万円に引き上げられます。賃金と老齢厚生年金の合計が月62万円未満ならば、年金の減額や支給停止はありません。なお、老齢基礎年金は従来どおり減額されません。
【例】賃金月46万円、老齢厚生年金の受給額が月10万円、老齢基礎年金が月6万9千円の場合
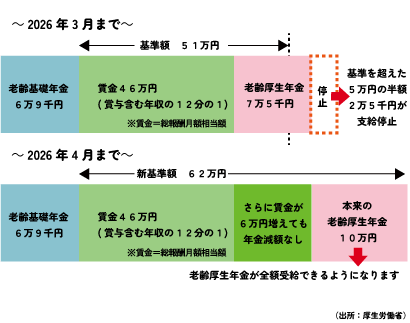
2.在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式
[1]基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)との合計が62万円(※3)以下の場合 ⇒ 全額支給
[2]基本月額(※1)と総報酬月額相当額(※2)との合計が62万円(※3)を超える場合
⇒ 基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−62万円(※3))÷2
(※1)基本月額とは、老齢厚生年金の月額
(※2)総報酬月額相当額とは、賞与を含む年収の12分の1
(※3)新基準額である62万円は毎年度見直される可能性あり
※人事評価制度の構築・見直し・運用の支援についてお問い合わせをお待ちしています〜
|