| 平成24年4月号 | |||
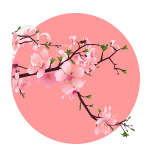 |
|||
| 3月14日に自動車、電機、造船・重機、鉄鋼などの主要企業が一斉に春季労使交渉に対する回答を行いました。今年も東日本大震災、タイの洪水、欧州の財政不安に伴う世界的な景気低迷、円高など深刻な環境の中での春闘となりました。そこで要求段階で多くの組合が賃金改善要求を見送った上で、定期昇給の維持と一時金の上積みを求めるのみとなりました。会社側は固定費増加を嫌い、賃金改善は4年連続でゼロ、定昇を維持するにとどまり、一時金についても前年実績を下回る回答が大半を占めました。しかし電機では韓国や台湾との競争が激しくなるなど業界全体が業績不振に陥っており、シャープは会社側から定昇凍結の提案、NECは賃金カットを要請などリーマン・ショック以来の厳しい結果となりました。 現在、多くの企業が労使協定に基づいた再雇用の条件を設けているため、組合は希望者全員が65歳以降も雇用されることを求めていました。 |
|||
|
|
|||
